こんにちは、しま農研です!しま農研では、毎年40種類以上の野菜を育てながら家庭菜園を楽しんでいます。プランター栽培も多く取り入れていますが、使い終わった土をどうするか 、悩んだことはありませんか?
「このまま捨てるのはもったいないし…」
「でも、そのまま使っても大丈夫?」
そんな方に向けて、しま農研流・再生材を使ったプランターの土のリサイクル方法 をご紹介します!
土の再生材を活用することで、古い土もふかふかで栄養たっぷりの土にリフレッシュ! 新しい土を買うよりも コストを節約できるだけでなく、環境にもやさしいので、しま農研でも実践しています。
この記事では、初心者でも簡単にできる土のリサイクル手順 を詳しく解説します。それでは、一緒にプランターの土をリフレッシュ していきましょう!

土の再生材を使うことで長い期間土を使い続けることができます。しま農研では土を捨てることなくプランター栽培楽しめています。
1.古い土を再利用する前に:プランター用の土ふるいで不純物を取り除こう!
古くなったプランターの土を再利用する際には、まず 不要なゴミや根、虫の幼虫を取り除くこと が大切です。
以前育てた植物の 根や雑草の種、枯れ葉 が残っていると、新しい野菜の成長を妨げてしまう可能性があります。特に 害虫の卵や幼虫 は見落としがちなので要注意です!
そこで活用したいのが 「土ふるい」 です。
✅ 土ふるいをするメリット
✔ 根やゴミを取り除き、土の通気性や水はけを改善
✔ 害虫の卵や幼虫を取り除く ことで、次の栽培への影響を減らす
1.1 土ふるいの手順

1️⃣ プランターの土をしっかり乾燥させる
➡ 軒下や雨が当たらない場所でしっかり乾燥させる(乾いた方がゴミを取りやすい!)
2️⃣ 乾燥させた土をふるいにかける
➡ ふるいを使って土と不純物を分ける。(根や害虫などがふるいに残るよ)
3️⃣ 残った根や害虫を取り除く
➡ ふるいに残った、根や害虫の幼虫を取り除く。(土の塊や小石などは土にもどす)
1.2 しま農研おすすめの土ふるい

プランターの土を再生するとき、土ふるいの作業は意外と大変です。そこで、しま農研では 「折りたたみ式の土ふるい」 をおすすめしています!
✅ 折りたたみ式ふるいのメリット
✔ コンパクトに収納できる ので、場所を取らない
✔ 軽量タイプが多く、持ち運びしやすい
✔ 一度にたくさんの土をふるうふことができる
市販の園芸用ふるいでも十分ですが、大きめのふるいを使うことで 土を一度にたくさんふるえる ため、作業効率もアップします。
さらに 「折りたたみ式で収納も簡単!便利なプランターでの土ふるいの使い方」 の記事では、しま農研が愛用している土ふるいについて詳しく解説しています。作業のコツや効率的な使い方も紹介しているので、ぜひチェックしてみてください!
2.土の再生材を選ぼう!
プランターの土を長期間使い続けると、次のような問題が発生することがあります。
✅ 団粒構造が崩れ、土が硬くなってしまう
✅ 栄養が不足し、野菜がうまく育たなくなる
✅ 塩分や有害物質が蓄積し、土が劣化する
こうした問題を簡単に解消できるのが 「土の再生材」 です!
再生材には、堆肥、コンポスト、腐葉土、木質チップ などが含まれており、これらを適切に混ぜることで、土に必要な栄養を補いながら水はけや保水性を改善し、土を健康な状態にリフレッシュすることができます。
2.1 土の再生材の種類と特徴
土の再生材にはさまざまな種類があり、メーカーごとに 配合成分や特徴に違いがあります。
例えば…
✔ パーライト・バーミキュライト配合 → 排水性を高め、土をふかふかにする
✔ もみ殻堆肥入り → 有機物を増やし、団粒構造の形成をサポート
✔ 善玉微生物配合 → 根の張りがよくなる
また、混ぜる量もメーカーごとに異なり、コストパフォーマンスにも差が出るため、選び方が重要です。
2.2 しま農研おすすめの再生材

「どれを選んだらいいかわからない…」という方のために、しま農研では 実際に使用した土のリサイクル材の情報をまとめた 「土のリ再生材の選び方とおすすめ6選」 という記事を作成しました。
この記事では、各リサイクル材の 特徴や使い方 を詳しく解説し、しま農研が 実際にその土の再生材を使って育てた野菜の成長の様子も共有しています。
「この再生材を使ったら、どんな土になるの?」「実際に野菜の育ち方に違いはある?」
そんな疑問を持つ方うや何を買おうか迷っている方にとって最適な土の再生材を見つけるヒント になれば嬉しいです!
3.土を再生する方法:再生材を混ぜて肥沃な土壌を作る
プランターの古い土をリフレッシュさせるために、最後の仕上げとして リサイクル材を混ぜ込み、肥沃な土壌を作りましょう!
ただし、 再生材は適量を守ることが大切 です。入れすぎると土のバランスが崩れ、かえって生育に悪影響を与えることもあります。各リサイクル材の 使用量の目安 を確認し、適切な量を混ぜ込むようにしましょう。
3.1 効果的な再生材の混ぜ方

リサイクル材の多くは、「上から撒くだけでOK」と記載されていることもありますが、 しま農研ではブルーシートに広げて、しっかりとまんべんなく混ぜる方法 をおすすめしています。この方法のメリットは以下の通りです。
✅ 再生材が均等に行き渡り、ムラなく土が再生される
✅ 団粒構造の回復を助け、ふかふかの土が作りやすい
✅ 不要な大きなゴミや虫を取り除きながら混ぜられる
さらに、 前回育てた野菜の種類を把握し、異なる科の野菜を育てると連作障害のリスクを減らすことが期待できます。
例えば:
✔ トマトを育てた後は、葉物野菜やマメ科の植物に変更する
✔ 同じナス科(トマト・ナス・ピーマンなど)の繰り返し栽培は避ける
こうした ちょっとした工夫で、土の負担を軽減しながら長く使えるようになります!
4.プランターの土の消毒方法:期間に余裕があればやってみよう!
プランターの土を再利用する際、病原菌や害虫の卵が残っていると、野菜が病気になったり生長が悪くなったりする可能性があります。
そこで、しま農研では2つの方法で消毒を行っています。
🌱 冬の消毒 → 寒起こし
☀ 夏の消毒 → 太陽熱消毒
👉 消毒は必須ではありませんが、効果的に行うことで土の状態をリセットしやすくなります!
4.1 冬の土の消毒方法:プランターでの寒起こし
プランターの古い土を再利用する際に、 寒起こし という方法を試してみませんか? 冬の寒さを活かして 病原菌や害虫を抑えることができ、自然の力で土を消毒する手軽な方法です。
ただし、 寒起こしだけで完全に病原菌を除去できるわけではない ので、補助的な対策として取り入れるのがおすすめです。
4.1.1 寒起こしのやり方
実際の手順はとても簡単です。 冬の寒さと霜の力 を利用して、自然に土をリフレッシュさせましょう。特に 霜が降りる地域では効果が高く、寒さによって土壌内の害虫や病原菌が減少すると言われています。
しま農研では、 「地植えでの寒起こし作業を詳しく紹介している記事」を作成しています。興味のある方はぜひ参考にしてみてください!
4.2 暖かい日の土の消毒作業:プランターでの太陽熱消毒
春から夏にかけての暖かい季節には、 太陽の熱を利用した消毒がおすすめです。特に 真夏の強い日差し を活用すれば、 病原菌や害虫の減少効果が期待できます。
しま農研では、期間に余裕がある時はプランターの土をリセットするためにこの方法を取り入れています。自然の力で土を清潔にするので、簡単で効果的な方法です!
太陽熱消毒のメリットやその方法については、「真夏がチャンス!太陽熱消毒でプランターの土を病害虫から守る」の記事で詳しく解説しています。動画や実践情報もありますのでこちらの記事もぜひ参考にしてください。
4.しま農研のプランター土作りレポート
しま農研では、実際のプランター栽培を通じて得られたデータをもとに、「プランター土づくりレポート」をまとめています。このレポートでは、さまざまな再生材を使った際の 土の状態や野菜の生長の違い を比較・検証しています。
2025年以降、使用した再生材ごとの実践結果を順次公開予定です。「どの再生材を選べばいいか迷っている…」という方は、再生材選びのヒントとして、ぜひ参考にしてください。
\ 実践データと野菜の育ち方が気になる方はこちら! /
5.まとめ
プランターの土は、一度使ったら捨てるのではなく、リサイクル材を活用して再生すれば、繰り返し使うことができます。新しい土を購入するよりもコストを節約できるだけでなく、適切に管理することで、より良い環境で野菜を育てることが可能になります。
土を再生させるためには、まずふるいにかけて根やゴミなどの不純物を取り除きます。その後、リサイクル材を適切な量混ぜ込み、土の栄養バランスを整えることが重要です。ブルーシートに広げてしっかりと混ぜることで、土全体にリサイクル材が行き渡り、ふかふかの土に生まれ変わります。
さらに、時間に余裕があれば、病原菌や害虫のリスクを軽減するための消毒を取り入れるのもおすすめです。冬の寒起こしや、夏の太陽熱消毒を活用することで、より健康な土へとリフレッシュできます。
プランターの土を再生することで、家庭菜園をもっと手軽に、もっと楽しく続けることができます。ぜひ今回紹介した方法を試して、元気な野菜を育ててみてください!
しま農研では、土作りに関するさまざまな情報を発信しています。具体的な土壌改良の方法については 「しま農研の土作りガイド:土作り関連記事のまとめ」 の記事もぜひ参考にしてみてください。
読んでいただきありがとうございました!






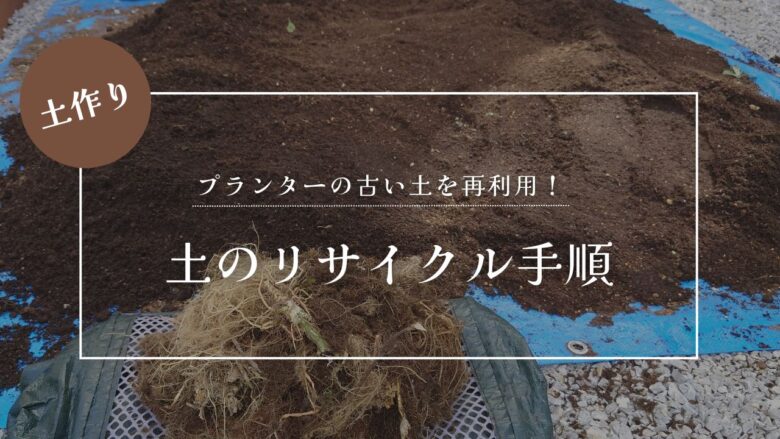







コメント