花オクラという花を食べるオクラに似た植物を知っていますでしょうか?花オクラはとても綺麗で観賞するだけでも楽しめるのですが、食べることもできます。ただ、スーパーではあまり見かけないことが多いです。
その理由として、収穫のタイミングや保存期間が短いためではないでしょうか。しかし、庭やベランダでの家庭菜園なら、これらのデメリットはあまり気になりません。加熱するととろっとしたオクラに似た食感になり、おひたし等で美味しく楽しめます。
この記事では、そんな魅力的な花オクラの育て方について詳しくまとめました。花もきれいなので、しま農研としても特におすすめの植物です。

花がとても綺麗でみているだけでも癒されます。とろっとした食感で食べても楽しめます。また、採種すれば毎年手軽に育てることができるのもおすすめです!
1.花オクラについて
花オクラはアオイ科トロロアオイ属に属する一年草で、その原産地は中国です。綺麗な花を咲かせ、通常のオクラに比べてやや大きな花が特徴です。育てる方法はオクラと似ています。オクラの栽培経験がある方なら、花オクラの栽培も難しくないでしょう。
| 和名/英語 | 花オクラ |
| 原産地 | 中国 |
| 分類 | アオイ科トロロアオイ属 |
| 発芽適温 | 25~30℃ |
| 生育適温 | 20~30℃ |
| プランター | 普通 |
| 土壌酸度 | pH6~6.5 |
| 収穫まで | 約1ヶ月 |
1.1 花オクラとオクラの違い
オクラと花オクラの主な違いは、食べる部分にあります。花オクラの特長は、その花を食べることができる点です。加熱すると独特のとろっとした食感になり、おひたしやおすまし、サラダなどで楽しむことができます。
その特性上、収穫後の保存期間が短いため、一般的なスーパーではあまり見かけない野菜となっています。
2.花オクラのプランターでの栽培計画と準備
2.1 花オクラ栽培のプランター大きさ
2.1.1 花オクラを育てるプランターを選ぶ
花オクラはオクラと同様に直根性のため、多湿を好まない特性があります。
正確な情報はまだ不足しているため、絶対的な確証は持てませんが、しま農研では10号の深さ30cm以上の深型プランターを使用して栽培しています。

2.1.2 プランターの選び方
プランターを選ぶ際は、サイズの「号」や「型」の表記を理解することが重要です。プランターの材質や形状も植物の健康に大きく影響します。
こちらの記事では、プランター選びのコツとおすすめのプランターについても詳しく紹介しています。プランター購入を検討している方は、ぜひこれらの情報を参考にしてください。
2.2 花オクラのプランターでの栽培計画
花オクラの発芽に適した温度は25~30℃です。この温度範囲になる5月中旬から6月初旬頃に播種するのが最適です。あまり早く播種すると、温度が低すぎるため芽が出にくいことがあります。栽培を進めると、8月頃から収穫が始まり、10月頃には採種作業を行います。
2.2.1 花オクラのプランター栽培カレンダー
しま農研での花オクラの栽培経験を基に、月別の具体的な作業と成長の様子をカレンダー形式でまとめました。このカレンダーを参照することで、花オクラの成長の進行や、それに伴うケアのタイミングを具体的にイメージすることができます。
栽培に先立って、このカレンダーを用いて予習することは、成功への第一歩となります。なお、このカレンダーに記載されているデータはしま農研での実際の結果をもとにしていますので、異なる環境や条件下での栽培時には参考程度にご利用ください。

2.3 花オクラのプランター栽培の土づくり
プランターで使用する土は、2年目以降も適切な手入れを行えば再利用が可能です。プランター栽培を初めて行う方は、園芸店で取り扱っている野菜用の土を購入するのがおすすめです。
具体的な土の処理としては、土からの古い根を取り除いた後、土の再生材を混ぜ込んで使用します。さらに、太陽熱消毒を行うことで、土の状態をより良くすることができます。具体的な土づくりの手順や詳細については、別の記事で詳しく解説しています。
3.花オクラのプランターでの栽培方法
この章では、プランターを使用した花オクラの栽培の具体的な手順を詳しく解説します。
3.1 花オクラの種まき(プランター)
花オクラは市販の株が少ないため、種から育てる方法が一般的です。その発芽適温は25~30℃であり、温度を特に管理しない場合、5月中旬から6月初旬に播種することを推奨します(早めの播種は芽が出づらくなることがあります)
3.1.1 プランターに直播
花オクラはオクラと違い移植をそれほど嫌わない傾向にありますが、プランターに直播で育てることは手軽なためおすすめです。
ただし、昨年、自分で採種したものを使う場合は発芽率があまり高くないことを考慮する必要があります。市販の種ですと3,4粒ほどでよいですが、プランターをに6~8粒ほど播き間引きする方がよいでしょう。
種まき
直径4~5cm、深さ1cmほどの穴を空け種をまき土をかぶせ軽く鎮圧します。
種まきが終わりましたらたっぷり水をあたえます。

3.2 花オクラの間引き(プランター)
3.2.1 間引きのタイミング
花オクラの間引きは栽培の重要な工程です。しま農研では、採取した種を直播し、通常より多めにまくため、発芽した本数に応じて適切に間引きを行います。この章では間引きの適切なタイミングについて解説します。
間引き1回目
発芽後、発芽率がよく芽が密集している状態であれば双葉が開いたタイミングで初めて間引きを行います。
この時、4~5本の元気の良い芽を残します。

間引き2回目
本葉が1枚出たタイミングで2回目の間引きを行います。
元気の良い苗を3本程度残し、1本仕立てにしない場合はこの工程で間引きは終了します。

間引き3回目
1本仕立てで育てる場合は、本葉が4~5枚に展開した時に行います。
虫の被害がなく、葉が大きく育っているものを残し、それ以外はハサミを使用して間引きます。

3.3 花オクラの収穫(プランター)
花オクラの収穫は、他の野菜や花とは少し異なる点があります。以下に詳しくその方法と注意点を説明します。
3.3.1 早めの収穫がポイント
花オクラの花の寿命は非常に短く、日の出と共に咲き、夜にはしぼんでしまいます。この特性のため、花が咲いたら迅速に収穫することが求められます。
この短い持続性が、スーパー等であまり目にすることが少ない理由となっています。

3.3.2 花オクラ収穫後の保存のコツ
収穫した花オクラは、雄しべを取り除き、花びらのみを残します。その後、水で十分に洗浄し、キッチンペーパーで水分をしっかりと取り除きます。
水分を取り除いた花オクラをキッチンペーパーに包み、密閉容器に入れて冷蔵庫での保存を推奨します。この方法により、数日間の保存が可能となります。
3.4 花オクラの摘葉と整枝【プランター】
3.4.1 通気性の確保と生育の促進
花オクラは成長するために良好な風通しを必要とします。風通しを確保し、また植物の成長を促進するための具体的な手順とポイントについて説明します。
わき芽の処理
花オクラのわき芽は伸びると風通しを悪くする可能性があります。そのため、伸びたわき芽は早めに取り除くことが推奨されます。
摘葉のポイント
収穫した花の部分から1-2枚の葉を残し、それより下の部分の葉は摘み取ります。この摘葉作業は、風通しを改善するだけでなく、栄養を植物の上部に集中させる効果も期待できます。
生育の注意点
もし葉の勢いが弱く、葉が小さくなっている、または植物全体がスカスカの状態の場合、その原因として植物の生育が弱まっている可能性が考えられます。このような場合、摘葉作業を控えることが必要となります。
3.5 花オクラの追肥
3.5.1 花オクラの追肥のポイント
花オクラの追肥に関する具体的な情報は限られていますが、しま農研の経験として、オクラの似通った特性を参考に追肥の方法にしています。まず、追肥の開始は初めての花が咲いた直後にし、その後おおよそ2週間ごとに定期的に追肥を続けています。
花オクラの成長をよく観察して、花が成長点近くで咲き始めたり、葉の形が細くなったり、葉の切込みが深くなることは、肥料が不足している可能性を示唆しています。ただし、花オクラの葉は、オクラの葉に比べてもともと切れ込みが深い特徴があるため、その点を考慮しつつ追肥の判断を行うことが大切です。今後、栽培経験を増やしてより正確な情報を更新していきます。
| 肥料不足 | 適正 | 肥料過多 | |
| 花の咲く位置を観察 | 成長点に近いところで咲いている | 上に葉が3枚以上ある | 上に葉が5枚以上ある |
| 葉を観察 | 葉の切込みが深い | – | 葉の色が濃く丸い。切込みが浅い |


3.6.2 追肥作業の向上
追肥は植物との対話とも言える作業で、正しい方法を見つけるためには経験と観察が必要です。植物の細かな変化に注意を払い、追肥の技術を磨くことで、野菜とのやり取りがより楽しく、生産的なものになります。
追肥に関するさらに詳しい手法や考え方については、しま農研の別の記事で詳しく解説しています。現在も追肥に関する研究を続けているため、興味がある方はぜひ参考にしてみてください。
追肥の基本的な考え方を知っておくと、適切な肥料の与え方に近づくことができます。しま農研では追肥についての記事をまとめています。よろしければ参考にしてください。
3.7 花オクラの水やり
花オクラをプランターで栽培する際の一つの難点は水切れの問題です。土が乾いた状態や花オクラの葉がしなっとした状態が、水切れのサインとして現れます。これを目安にして、水やりを行うタイミングを見極めることが肝心です。
葉がしなっとした場合でも、適切な水やりを行えば花オクラは元気に復活します。ただし、これを避けるためには、季節や天候に応じて水やりの頻度や量を調整することが大切です。特に真夏は、暑さが厳しい日中よりも、朝早くや夕方の涼しい時間帯に水やりをすることがおすすめです。

3.8 花オクラの種取りと保管
花オクラの種を取ることで、来年も同じ花を楽しむことができるのは魅力的です。種取りはそんなに難しい作業ではありませんが、いくつかのポイントを抑えて行うことが大切です。
1.花オクラの種採り
まず、種を採るためには花を放置し、実にする必要があります。しかし、収穫の初期や中盤で実をつけると、その株の生長や花の生産に影響が出ることがあるので、収穫の終盤、花が少なくなってきた時期を選ぶとよいです。
実が十分に成熟して茶色くなったら、その実から種を取り出します。取り出した種が湿っている場合は、風通しの良い場所できちんと乾燥させることが必要です。

2,花オクラの種の保管
種の保管に関しては、環境をしっかりとコントロールすることが大切です。低温、低湿、暗所での保管が理想的です。冷蔵庫はその条件を満たすのでおすすめですが、冷蔵庫に入れるのが難しい場合でも、直射日光を避けて、20℃以下の涼しい場所に保存します。
また、種が湿気を吸収しないように、乾燥剤を一緒に保管すると、種の品質がより長持ちします。
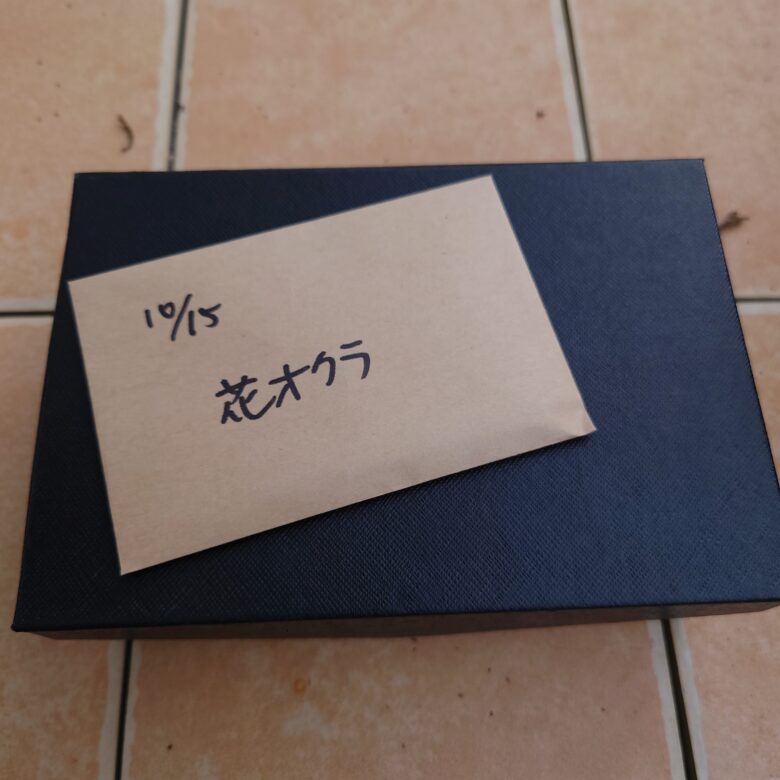
4.しま農研のプランターでの花オクラ栽培:実践編
しま農研では花オクラのプランター栽培に関する実践を進めており、独自の試みや遭遇するトラブルを通じて多くを学んでいます。この章では、その栽培の実際の様子を共有し、あなたが花オクラ栽培を行う際の貴重な参考情報を提供することを目指します。
4.1 花オクラのプランター栽培の観察記録
しま農研での日々の栽培活動は、花オクラの成長をリアルタイムで観察し、その記録を共有しています。これにより、効果的な栽培方法を継続的に評価し、改善することが可能です。また、最適な栽培技術を見つけ出すための試みも進行中です。
これらの詳細な観察記録を活用し、あなたの花オクラ栽培における成長の比較や問題解決の参考としてください。
4.2 しま農研の花オクラの栽培レポート
しま農研では花オクラのプランター栽培の過程を実際に観察し、「花オクラの栽培レポート」として詳細にまとめています。このレポートには、月ごとの成長記録や日常のケアの様子が含まれています。これにより、あなたの栽培の参考や目安としての活用ができるようにしています。
家庭菜園には多くの疑問や課題が存在します。そのため、しま農研はこれらの疑問や課題に対して実際の検証や考察を行っております。失敗した実例を含む多岐にわたるテーマについてレポートしています。
花オクラのプランター栽培に関するさらなる疑問や課題がある方は、ぜひこちらのレポートも参考にしてください。
5.まとめ
この記事では、花オクラのプランター栽培について詳しくまとめました。プランターの選び方から栽培計画、具体的な栽培作業までを解説しました。
花オクラは庭を鮮やかにしてくれ癒されるため、しま農研では栽培計画に毎年組みたくなる育てて楽しい植物です。市販ではあまり流通しないため。食べる機会も少ないため家庭菜園ならではの楽しみもあります。少し変わった植物を育てたい方には特におすすめです。
また、しま農研ではさまざまな野菜の栽培方法を紹介しています。記事は50音順で整理され、アクセスしやすい形になっています。興味がある野菜の情報も手軽に探せますので、是非ご活用ください。
読んでいただきありがとうございました!









コメント