こんにちは!しま農研です。しま農研では毎年30種類以上の野菜を育てて、家庭菜園を思いっきり楽しんでいます。
落花生を育てたことはありますか?
家庭菜園で育てる落花生は、採れたてならではの「ほくほく食感」とやさしい甘みが楽しめる、市販とはひと味違う特別な体験ができる野菜です。
家庭菜園のメインシーズンであるゴールデンウィークを過ぎても栽培に間に合うのも嬉しいポイント。
さらに、根っこにつく根粒菌は土に良い影響を与え、トマトやナスなどのコンパニオンプランツとしても活躍します。
この記事では、しま農研が実践している落花生の地植えでの育て方を詳しくご紹介します。
今年は、自分で育てた落花生で、採れたての美味しさを味わってみませんか?🌱

落花生はコンパニオンプランツでしま農研も採用する野菜です。鳥にも注意しながら収穫まで頑張ろう!
1.落花生について
家庭菜園を始める前に、まずは落花生の基本的な特徴を知っておきましょう。植物の特性を理解しておくことで、栽培への興味も高まり、より楽しく育てることができます。
落花生の原産地は、南米アンデス山麓と言われています。最大の特徴は、花が地面に落ち、そのまま地中で実を結ぶこと。土の中に入った子房が水分を吸収し、莢(さや)や種子を形成します。このため、落花生を育てる際は、子房が土に入りやすい状態を作ることがポイントです。
また、落花生の原産地はトマトと同じく南米アンデス山麓。相性の良いコンパニオンプランツとしてトマトと一緒に植えるのもおすすめです。原産地の環境を想像しながら栽培すると、家庭菜園の楽しみもさらに広がります。
| 和名/英語 | ラッカセイ |
| 原産地 | 南アメリカ |
| 分類 | マメ科〇〇属 |
| 発芽適温 | 20~30℃ |
| 生育適温 | 25~28℃ |
| 株間 | 30~40cm |
| 土壌酸度 | pH6~6.5 |
| 収穫まで | 約5ヶ月 |
2.地植えでの落花生の栽培計画と準備
落花生を地植えで育てるためには、事前の準備がとても重要です。このセクションでは、栽培時期・栽培スペース・土づくりなど、落花生を元気に育てるための基本的なポイントをご紹介します。
2.1 落花生の栽培時期
落花生の植え付け適期は地域や気候によって異なりますが、中間地では5月中旬から6月上旬頃が目安です。十分に気温が上がってから植え付けると、発芽や初期生育がスムーズに進みます。
種まきから約100〜120日ほどで収穫期を迎えるのが一般的です。落花生は移植をあまり好まないため、直播きがおすすめですが、気温が安定しない時期はポット育苗からの定植も可能です。
市販の苗を利用すれば、家庭菜園初心者の方でも手軽にスタートできます。
2.2 落花生の栽培スペース
落花生は地面に子房柄(しぼうへい)が伸びて土中で実をつける特性があるため、広めのスペースと柔らかい土壌が必要です。また、品種により株張り形状が違い生長に違いがあるため注意が必要です。
- 畝幅:60cm程度(2条植え)
- 株間:株間30~40cm
📌 品種の違い
立性・・・茎が直立しており、枝が上向きに伸びるため、株張りがコンパクト
ほふく性・・・枝が地面を這うように伸びるため、株張りが広がり、地面を覆うように育つ
2.3 落花生の土づくり
土づくりは、落花生を含む多くの野菜にとって栽培成功の土台を築く重要な作業です。晩冬から春にかけて、じっくりと時間をかけて準備を進めましょう。植え付け予定日の1ヶ月前には作業を始めておくのが理想です。
適切な土づくりには、雑草の除去、土壌の改良、酸度の調整、そして元肥の施用が含まれます。これらの手順については、「春夏野菜の土作り手順と時期」の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
3.地植えでの落花生の育て方
この章では、地植えでの落花生の育て方について、種まきから収穫、管理方法まで、しま農研の実践をもとにわかりやすくご紹介します。
3.1 落花生の種まき(地植え)
落花生は発芽適温が20~30℃のため、十分に暖かくなってから種まきを行います。中間地では、5月中旬から6月上旬頃までが適期です。しま農研では、この時期に種をまく場合、栽培スペースに直接まく「直播(じかまき)」を採用しています。
株間は、立性や半立性の品種では30~40cm、おおまさりなどのほふく性の品種は少し広めにとるとよく育ちます。
3.1.1 落花生の種まき手順
- 種まき用の穴を空ける
植え付け場所に、直径約5cm・深さ1~2cmの穴を空けます。 - 種をまく
開けた穴に2~3粒ずつ種をまきます。 - 覆土して水やり
種に覆土したら、軽く手で押さえて土を密着させます。その後、たっぷりと水を与えましょう。鳥などが心配な場合は、芽が出るまで不織布などをかけて鳥よけ対策をしておくと安心です。
3.2 落花生の間引き(地植え)
落花生は、仕立てる本数に応じて間引きを行います。仕立てる本数は人それぞれ異なりますが、ここでは「1本仕立て」をベースにご紹介します。
📅【間引きのタイミングと残す本数】
| 回数 | タイミング | 残す本数 |
|---|---|---|
| 1回目 | 本葉が2枚の頃 | 2本残す |
| 2回目 | 本葉が3〜4枚の頃 | 1本残す |
※草丈が10cm程度になれば、鳥の被害はほとんどなくなります。生長に応じて、不織布やネットは取り外しましょう。また落花生は初期成育が遅いため、この時期は他の草に負けないようにこまめに除草をしておくと成功に繋がります。
🌱【間引きのポイント】
- ハサミで根元から丁寧に切ることで、残す株の根を傷つけにくくなります。
- 生育が良く、葉色が濃く茎がしっかりしている苗を選びましょう。
3.3 落花生の追肥と中耕・土寄せ(地植え)
土作りがしっかりできていれば、花が咲くまでは追肥はほとんど必要ありません。
ただし、生長が遅い、葉の色が薄いなどの症状が見られる場合は、適宜追肥を行いましょう。
3.3.1 落花生の追肥・中耕・土寄せのタイミング
落花生は花が咲いた後、子房柄(しぼうへい)が土に潜り、サヤや実が育つため、土を柔らかく保つことがとても重要です。追肥のタイミングに合わせて、中耕(土をほぐす作業)や土寄せも行い、子房柄が土に入りやすい環境を整えましょう。
📅【追肥・中耕・土寄せのタイミング表】
| 回数 | タイミング | 追肥 | 中耕 | 土寄せ |
|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 花が咲き始めた頃 | 行う | 行う | 行う |
| 2回目 | 1回目から15〜20日後 | 行わない | 行わない | 行う |
🌱【作業のポイント】
- 1回目(花が咲き始めた頃)
熊手などで株元の土を軽くほぐし、肥料を混ぜ込みながら中耕します。最後に株元に土を集めて土寄せを行います。 - 2回目(15〜20日後)
子房柄がたくさん土に潜り始める時期です。この段階で瓶、子房柄を傷つけるリスクがあるため、中耕や追肥は行わず、土寄せのみを行いましょう。
3.4 落花生の収穫(地植え)
落花生は、開花から80〜100日ほど経過し、葉の一部が黄色く枯れてきたら収穫のサインです。取り遅れると豆が熟しすぎて子房柄が切れ、収穫しにくくなるため注意しましょう。
網目模様がはっきりし、子房がしっかり膨らんでいれば、ちょうどよい収穫時期です。
3.4.1 落花生の収穫手順
- 土をほぐす
株のまわりにスコップを差し込み、土を柔らかくします。 - 株を引き上げる
株元を持って、ゆっくりと引き上げましょう。 - 取り残しをチェック
最後に、土の中に取り残したサヤがないかしっかり確認します。
📌【収穫後の楽しみ方】
落花生は乾燥させて保存もできますが、採れたてを茹でて味わうのがおすすめです。ほくほくとした食感とやさしい甘みは、市販品ではなかなか味わえない特別な美味しさですよ。
4.よくある落花生の疑問Q&A【しま農研の実体験から】
この章では、よくある落花生の疑問に、しま農研の実体験からお答えします。あなたの「これで大丈夫かな?」が少しでも解決できれば嬉しく思います。
4.1 落花生はコンパニオンプランツとして使える?
落花生は、根に共生する根粒菌(こんりゅうきん)が土壌に窒素を供給し、一緒に植えた野菜の生育を助ける働きがあります。
特に、ナス科の植物とは相性が良く、しま農研でもナスやトマトとの混植栽培を実践しています。
なかでもトマトは、落花生と同じ南米アンデス山麓が原産で、出身地が近いことも相性の良いポイントです。
しま農研では、毎年さまざまな混植栽培にチャレンジしながら、コンパニオンプランツの研究も進めています。
👉 「コンパニオンプランツまとめガイド」では、混植栽培に関する情報をまとめています。興味のある方はぜひご覧ください。
4.しま農研の地植えでの落花生栽培:実践編
しま農研では、地植えによる落花生の栽培を実践しながら、さまざまな工夫や問題点の発見、改善に取り組んでいます。
この章では、実際の栽培の様子や気づきを共有することで、落花生栽培に取り組む方のヒントになれば嬉しいです。
4.1 落花生の地植え栽培の観察記録
しま農研では、落花生の種まきから間引き、追肥、収穫までの様子をリアルタイムで観察・記録しています。
地植え栽培の場合は、トマトなどとの混植栽培も家庭菜園ではおすすめです。
今年は、しま農研でもトマトと落花生の混植栽培にチャレンジしています。
こうした記録は、気候や栽培条件によって変わる生育の判断材料になるだけでなく、ご自身の落花生栽培と比較するヒントにもなるはずです。
👉 「今どんなふうに育っているの?」と思った方は、ぜひこちらをご覧ください。
トマトと落花生の混植栽培リアルタイム観察記録
5.まとめ
落花生は、栽培の工夫次第で家庭菜園でもしっかり収穫が楽しめる野菜です。
育てる過程では、土の柔らかさや中耕・土寄せなど、少しの工夫が実りの多さに繋がります。
何より、自分で育てた落花生を掘り起こし、採れたてを茹でて味わうほくほくの美味しさは格別です。市販ではなかなか味わえない、この特別な体験は家庭菜園ならではの楽しみです。
ぜひ今年は、落花生栽培にチャレンジして、自分だけの「ほくほく茹で落花生」を味わってみませんか?🌱
また、しま農研では多様な野菜の育て方を50音順や科ごとでまとめたページもご用意しています。興味のある野菜の育て方をすぐに見つけられますので、ぜひこちらもご活用ください。
最後まで読んでいただきありがとうございました!






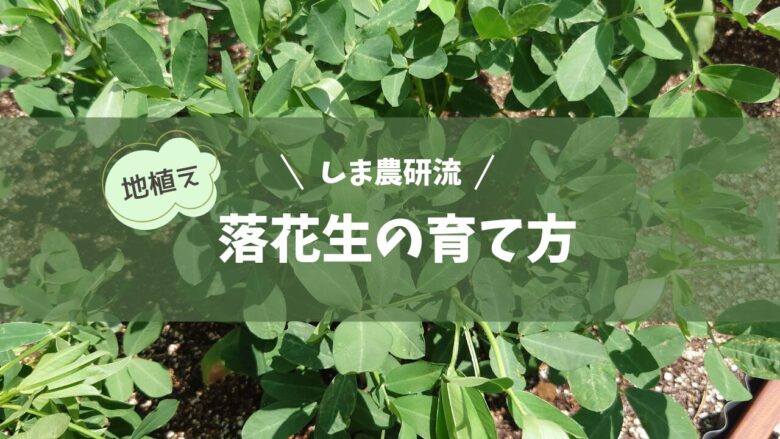






コメント