こんにちは!しま農研です。私たちは毎年30種類以上の野菜を庭で栽培し、家庭菜園の魅力を日々体感しています。
オクラは夏の定番野菜として人気がありますが、じつは花がとても美しいことをご存じですか?淡い黄色の花は、庭や畑の菜園スペースに癒しを与えてくれます。また、オクラは株間をあまり広くとらなくても育てられるため、ちょっとした地植えスペースでも数多く栽培できるのが魅力です。
この記事では、家庭菜園での地植えオクラの育て方を、初心者の方にもわかりやすく紹介していきます。種まきから下葉の整理、収穫のコツまで、しま農研の実践にもとづいたポイントをまとめていますので、栽培前の準備や畑での確認にぜひご活用ください!

オクラは、その昔は観賞用として楽しまれていたそうです。美しい花も育てる楽しみの1つです!
1.オクラについて
オクラの栽培を始める前に、その原産地や特性について少し学んでみましょう。基本を知っておくことで、栽培のコツがより明確になり、家庭菜園での育て方に自信が持てるようになります。
オクラの原産地はアフリカ東北部、特にエチオピア周辺とされており、高温で乾燥気味の気候の中で育ってきた野菜です。乾燥や暑さに強く、しっかりとした太い根を地中に伸ばして水分を吸収するのが特徴です。
また、原種のオクラは数株ずつまとまって自生していることから、1ヶ所に複数株を育てる栽培にも適しています。株間をあまり広くとらなくても育てやすいため、コンパクトな地植えスペースでもしっかりと収穫が楽しめます。家庭菜園にぴったりの夏野菜と言えるでしょう。
| 名称 | オクラ/アメリカネリ |
| 原産地 | アフリカ北東 |
| 分類 | アオイ科トロロアオイ属 |
| 発芽温度 | 25~30℃ |
| 生育適温 | 20~30℃ |
| 株間 | 30cm(1株) 40~50(3,4株) |
| pH | pH6~6.5 |
| 収穫まで | 約2ヶ月 |
1.1 プランターでのオクラの育て方
この記事では地植えでのオクラ栽培に焦点を当てていますが、オクラはプランターでも育てることができます。プランター栽培では、スペースの制約や水やりの頻度など、地植えとは異なる管理ポイントがいくつかあります。
具体的なオクラのプランターでの育て方については、下記の記事で詳しく解説しています。地植え栽培とあわせて検討している方は、ぜひこちらも参考にしてみてください。
2.地植えでのオクラの栽培計画と準備
オクラを地植えで育てるためには、計画的な準備が欠かせません。このセクションでは、栽培時期や栽培スペース、土づくりなど、オクラの地植え栽培を始める前に押さえておきたい基本的なポイントをご紹介します。
2.1 オクラの栽培時期
オクラの植え付け適期は地域や気候によって異なりますが、中間地では5月から6月上旬が目安です。オクラは高温を好み、発芽・生育ともに25~30℃が適温とされています。そのため、地温がしっかり上がってから種まきや定植を行うのが成功のポイントです。
種まきから約60日前後で収穫が始まります。オクラは移植を嫌う性質があるため、直播きで育てるのもおすすめです。ただし、早めに育てたい場合は、保温対策をしながらポットで育苗し、十分に気温が上がってから定植するとスムーズです。市販の苗を購入して植え付ける方法でも、手軽に栽培を始められます。
2.2 オクラの栽培スペース
オクラは太く深く伸びる直根を持つため、根をしっかり張れるスペースがあると健やかに育ちます。また、草丈は1m以上になるため、風通しと日当たりの良い場所を選ぶのが理想です。
地植えの場合、畝幅は60cm程度が目安です。1本仕立てで育てる場合は株間25〜30cm、3〜4本仕立てで育てる場合は40〜50cmほど空けるとよいでしょう。
2.3 オクラの土づくり
土づくりは、オクラを含む多くの野菜にとって栽培成功の土台を築く重要な作業です。晩冬から春にかけて、じっくりと時間をかけて準備を進めましょう。植え付け予定日の1ヶ月前には作業を始めておくのが理想です。
適切な土づくりには、雑草の除去、土壌の改良、酸度の調整、そして元肥の施用が含まれます。これらの手順については、「春夏野菜の土作り手順と時期」の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
オクラは深く根を伸ばすため、元肥は「溝施肥」にするのもおすすめです。底に施した肥料を求めて根が地中深くまで伸び、より丈夫に育ちやすくなります。
3.地植えでのオクラの育て方
この章では、地植えでのオクラの育て方について、種まきから収穫、管理方法まで、しま農研の実践をもとにわかりやすくご紹介します。
3.1 オクラの種まき(地植え)
オクラは発芽適温が25~30℃と高く、寒さに弱い野菜です。中間地では、5月中旬から6月上旬に種をまくのが最適です。地温がしっかり上がっていることを確認してから播きましょう。
オクラは移植を嫌うため、しま農研では直播きを基本としています。1ヶ所に、育てたい本数に対して+2〜3粒ずつ種をまき、株間は25〜30cm(1本立て)、40〜50cm(3〜4本立て)を目安にスペースを空けています。
3.1.1 オクラの種まき手順
1. 種まき用の穴を空ける
植え付け場所に、直径約5cm・深さ1cmの穴を空けます。オクラは好光性種子のため、浅めの穴にまくのがポイントです。
2. 種をまく
仕立てる本数に対して、2〜3粒多めに播いておくと、発芽しなかったときのリスクを回避できます。たとえば、1本育てたい場合は3〜4粒を播くようにします。
3. 覆土して水やり
種を覆土したら、軽く手で押さえて土を密着させます。その後、たっぷりと水を与えます。発芽するまでは、土が乾燥しないように適度な湿り気を保つことが大切です。
3.2 オクラの間引き(地植え)
間引きは、発芽した複数の芽の中から育てていく苗を選ぶ大切な作業です。健康な苗をしっかり選び、余分な芽は根元からハサミでカットして整理しましょう。
間引きは2回に分けて行うのが基本です。以下のようなタイミングで、仕立てたい本数に合わせて本数を減らしていきます。
| 間引きの回数 | タイミング | 残す本数 |
|---|---|---|
| 1回目 | 本葉が1〜2枚の頃 | 仕立てる本数+1 |
| 2回目 | 本葉が3~4枚の頃 | 最終的に育てる本数に決定 |
たとえば、1本仕立てなら最終的に1本、3〜4本仕立てなら、その本数に合わせて元気な苗だけを残します。
🌱 間引きのポイント
- 双葉のあとに出てくるギザギザした葉が「本葉」です。
- ハサミで根元から丁寧に切ることで、残す株の根を傷つけにくくなります。
- 生育がよく、葉の色が濃くて茎がしっかりしている苗を選びましょう。
3.3 支柱と風対策(地植え)
地植えで育てるオクラは、基本的に支柱は必要ありません。オクラは深く根を張る性質があるため、他の野菜に比べて倒れにくく、比較的安定した姿で育ちます。
ただし、複数本仕立てで茎が細く育ってしまった場合や、風が強い地域では、倒伏のリスクがあります。そのような環境では、支柱を立てて麻紐などで株元を軽く固定してあげると安心です。
3.4 オクラの収穫(地植え)
オクラは、種まきから約60日ほどで収穫が始まります。収穫はハサミを使い、実のつけ根から丁寧に切り取るのが基本です。
ベストな収穫タイミングは、開花から4〜5日後。品種によって最適なサイズは異なりますが、一般的な目安は以下の通りです:
- 五角オクラ:長さ6〜7cm前後
- 丸オクラ:長さ12〜15cm前後
いずれの品種も、若くて柔らかいうちに摘み取ることが大切です。大きく育ちすぎると、筋が入って食感が硬くなってしまいます。
🌱 収穫はこまめに!
オクラは生長がとても早いため、1〜2日で一気に大きくなりすぎることもあります。収穫期に入ったら、毎日チェックするつもりで観察しましょう。
3.5 オクラの下葉かき(地植え)
オクラを元気に育てるためには、風通しの確保と株の健康管理が大切です。そこで行うのが「下葉かき」と呼ばれる作業です。
基本的には、収穫した実の1〜2節下の葉を残し、それより下の葉を取り除くようにします。この作業を定期的に行うことで、次のようなメリットがあります:
- 株元の風通しが良くなり、病害虫の予防になる
- 栄養が上部や実にまわりやすくなる
ただし、葉の勢いが弱いときや、株全体が小さく元気がない場合は、下葉かきを控えた方がよいこともあります。あくまで生育状況を見ながら柔軟に対応することがポイントです。
3.6 オクラの追肥(地植え)
オクラの追肥は、一番花が咲いたタイミングからスタートします。その後は、2〜3週間に1回程度を目安に追肥を行いましょう。
特に真夏の収穫期には、株が多くの実をつけるため、栄養の消耗が激しくなります。追肥は欠かせない管理作業ですが、与えすぎには注意が必要です。過剰な肥料は葉ばかりが茂ったり、害虫を引き寄せやすくなったりする原因にもなります。この傾向は、他の野菜より強くみられます。
✅ 肥料切れのサイン
以下のような変化が見られたら、肥料が不足している可能性があります:
- 花が成長点(株の先端)近くに集中して咲いている
- 葉の切れ込みが深くなる(葉が細く鋭くなる印象)
追肥は、植物との対話のような作業です。マニュアル通りに与えるのではなく、株の様子をよく観察しながら調整することが大切です。もっと詳しく追肥について知りたい方は、しま農研の以下の記事もぜひ参考にしてください。らに詳しく深掘りしたい方はぜひ参考にしてください。
3.7 オクラの水やり(地植え)
地植えで育てるオクラは、基本的に水やりの必要はありません。オクラは乾燥に強く、アフリカのステップ地帯が原産の野菜です。深く根を伸ばして土中の水分をしっかり吸収するため、通常の天候であれば自然の雨だけで十分に育ちます。
逆に、過湿には弱い性質があるため、梅雨の時期などは表面が乾いていても、無理に水やりをしない方が良いこともあります。
☀️ 真夏の水やりは必要なことも
ただし、真夏になって晴天が何日も続き、雨がほとんど降らないような状況では、水分不足になることがあります。
そのような場合は、朝か夕方の涼しい時間帯に、株元から深く浸み込むようにたっぷりと水を与えましょう。表面だけを濡らすのではなく、地中深くまで届くような水やりが効果的です。
3.8 オクラの害虫対策(地植え)
夏の中頃から秋にかけて、オクラにはワタノメイガやオオタバコガといった害虫が発生しやすくなります。これらの害虫は、放っておくと実や葉を傷めてしまうため、早めの発見と対処が重要です。
| 害虫名 | 特徴・見分け方 | 対処法 |
|---|---|---|
| ワタノメイガ (ハマキムシ) | – 葉が巻かれて筒状になっている – 中に黒い粒(糞)がある | 葉を開いて幼虫を見つけ次第、手で駆除する |
| オオタバコガ | – 実に穴が空いている – 実が不自然に曲がる – 花がしぼんだ後に中に幼虫がいることも | 被害果は早めに摘み取って処分する |
しま農研でも、これらの害虫にはよく悩まされます。早期発見、駆除がポイントです。特に害虫の活動が活発になる8〜9月はこまめに観察しましょう。
3.9 オクラの種取り(地植え)
地植えでもオクラの種取りは十分可能です。ただし、種をしっかり成熟させるためには、実を約2ヶ月間放置する必要があり、その間ずっと菜園スペースを使うことになります。
後作に「スナップエンドウ」を育てることもおすすめです。11月頃に種をまくことで、オクラの茎に沿ってつるが伸び、スペースを効率的に活用できます。
🌱 種取りのポイント
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 1. 実を残す | 種取り用に実を残し、さやが茶色に変わり、割れ始めるまで放置する(2ヶ月程度) |
| 2. 乾燥させる | 収穫後、さやから種を取り出し、雨の当たらない場所でしっかり乾燥させる。 |
| 3. 保存する | 種が完全に乾いたら、封筒などに入れ、日光の当たらない涼しい場所で保管する。 |
4.しま農研の地植えでのオクラ栽培:実践編
しま農研では、地植えによるオクラの栽培を実践しながら、様々な工夫や問題点の発見、改善の取り組みを進めています。この章では、実際の栽培の様子や気づきを共有することで、オクラ栽培に取り組む方々のヒントや参考になればと思っています。
4.1 オクラの地植え栽培の観察記録
オクラは、生育スピードが早く管理のタイミングが重要な野菜です。しま農研では、種まきから間引き、支柱立て、収穫、追肥までの様子をリアルタイムで観察・記録しています。
今年は「3本仕立てと1本仕立て」による生育比較も実施中です。株ごとの生長スピードや収穫量の差がどう出るのか、具体的に観察していきます。
これらの記録は、気候や条件によって変わる生育の判断材料になるだけでなく、ご自身のオクラ栽培と比較するヒントにもなるはずです。
👉「今どんなふうに育っているの?」と思った方は
【2025年版】しま農研のオクラの地植え栽培リアルタイム観察記録 をご覧ください。
5.まとめ
この記事では、地植えでのオクラの育て方について、基本情報から実践的な管理方法、しま農研での取り組みまでをご紹介しました。
オクラは暑さに強く、家庭菜園でも育てやすい野菜のひとつです。特に地植えでは、深く根を張ってぐんぐん育ち、条件が合えば長期間にわたって収穫が楽しめます。淡い黄色の美しい花や、こまめな収穫の楽しみも魅力のひとつです。
🌿 栽培のポイントまとめ
- 種まきは気温と地温が安定してから(中間地では5月中旬〜)
- 間引きは2回に分けて、生育のよい苗を選ぶ
- 支柱は状況に応じて設置を検討
- 収穫は早め早めに、柔らかいうちに摘み取る
- 追肥や下葉かきは、株の状態を見ながら調整
- 害虫対策はこまめな観察がカギ
- スペースに余裕があれば、種取りにもチャレンジ!
しま農研では、毎年の栽培記録を通じて、よりよい育て方を探り続けています。あなたのオクラ栽培にも、今回の内容が少しでも役立てば嬉しいです。
また、しま農研では多様な野菜の育て方を50音順や科ごとでまとめたページもご用意しています。興味のある野菜の育て方をすぐに見つけられますので、ぜひこちらもご活用ください。
読んでいただきありがとうございした!













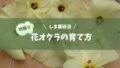
コメント