こんにちは、しま農研です!
しま農研では、毎年30種類以上の野菜を育てながら、家庭菜園の楽しさを日々実感しています。
春夏野菜の栽培で、「いつ追肥をすればいいのか?」と迷ったことはありませんか?
野菜の種類ごとにさまざまな説明があるため、「結局いつがベストなの?」と戸惑ってしまう方も多いかもしれません。
でも実は、花の咲き方・葉の色・実のつき方など、野菜が見せる“サイン”を観察することで、追肥のタイミングを見極めるヒントがたくさん得られるんです。
この記事では、しま農研の栽培経験をもとに、「花・葉・実・時期」から判断する追肥のタイミングのコツをわかりやすくご紹介します。
初心者の方でもすぐに実践できる内容になっていますので、ぜひご自身の菜園でも参考にしてみてください!

野菜がみえる”サイン”が分かってくると植物の小さな変化にも気づけて家庭菜園がさらに楽しくなります!
1. 花から読み解く追肥タイミング
野菜の花のつき方や様子には、肥料の過不足が表れるヒントが隠されています。
花の美しさを楽しみながら、「ごはん(栄養)は足りてるかな?」という気持ちで観察してみましょう。
1.1 雄しべと雌しべの長さを見てみよう!
こちらはナスの花の写真です。
花の中心にある、スッと一本伸びた部分が「雌しべ」、その周囲の黄色い部分が「雄しべ」です。
✅ 理想の状態は…
雌しべが雄しべより長く伸びていること。
これは、株に十分な栄養がある証拠です。
❌ 肥料不足のサインは…
雌しべが雄しべより短くなっていると要注意。
栄養が不足し、うまく着果できない可能性があります。
さらに、花の色が薄くなるのも肥料切れのサインです。

実をつけるには、たくさんのエネルギー(栄養)が必要。
「今の体では実を育てられないよ〜」という、ナスからのメッセージかもしれませんね。
この“サイン”は、同じナス科のピーマンにも当てはまります。
育てている方は、花の様子を追肥の目安として、ぜひチェックしてみてください!
1.2 花をつく位置を確認しよう!
オクラは、美しい花も楽しめる野菜です。
でも、もし花が“先端”で咲いていたら…それは肥料不足のサインかもしれません。
🌱 通常のオクラは…
成長点(先端)は細胞分裂が活発で、どんどん伸びていくのが基本です。
そのため、花は茎の途中や葉の付け根など、下の方から順に咲いていくのが健康な状態です。
⚠️ 肥料不足のときは…
株の生長が鈍くなり、伸びなくなった先端で花を咲かせてしまうことがあります。
これは、体力が足りず「もう伸びられないけど、なんとか花を咲かせよう…」というオクラのサインかもしれません。

📝 注意したいのは、栽培後期の症状
しま農研でも、栽培後期に花が先端につく現象はよく見られます。
この場合は、株が十分に伸びきって高さの限界に達したことも考えられます。
そのときは、先端を摘心してわき芽を育てる方法がおすすめです。
しま農研でも、追肥と摘心を組み合わせて収穫を長く楽しむ工夫をしています!
1.3 元気に育ってるのに花がつかない?
「葉は大きく育ってるのに、なかなか花が咲かない…」
そんな経験、ありませんか?
実はそれ、肥料のあたえすぎ=肥料過多のサインかもしれません。
🌱 よくあるのがウリ科の野菜たち
きゅうり、ゴーヤ、かぼちゃなどは、肥料が多すぎると花よりも葉やつるばかりが元気に伸びてしまうことがあります。
「もっと大きくなってから実をつけよう!」という植物の自然な反応とも言えますね。
⚠️ 肥料過多のデメリット
植物にとって肥料は栄養ですが、与えすぎると“メタボ体質”に。
肥料を多く吸収した株は、病害虫の被害も受けやすくなるため注意が必要です。
💡 適切な量とタイミングを意識しよう!
「元気なのに花が少ない」と感じたら、いったん追肥をストップして様子を見るのもひとつの方法です。

2. 葉から読み解く追肥タイミング
野菜の葉は、植物の健康状態や栄養バランスをもっともよく表してくれます。
「色」「大きさ」「形」などをチェックすれば、追肥が必要かどうかのヒントが見えてきます。
2.1 葉の色が薄くなる
葉の色は、いろいろな野菜に共通する「肥料サイン」のひとつです。
「最近なんだか葉が黄色っぽいな…」と感じたら、それはチッソ不足のサインかもしれません。
チッソは、葉や茎の生長に関わるとても大切な栄養素。
これが足りなくなると、下の方の葉から順に色が薄くなり、最終的には黄色く変色していくことがあります。
特に以下のような時期は注意が必要です:
- 夏の高温期や雨が続いたあと(肥料分が流れやすい)
- 生長が盛んな時期(野菜がたくさんの栄養を必要とする)
そんなときは、追肥をして様子を見るのがおすすめ。
再び葉が元気な緑色を取り戻せば、追肥が効果を発揮した証拠です。

✅ 株全体の葉が淡い黄緑色になっていたら、追肥のサイン!
❌ ただし、水不足や根のトラブルでも葉が黄色くなることがあるため、周囲の状況も含めて判断することが大切です。
📝 また、古い葉は自然と黄色くなることもあるので、株の下部ばかりに注目しすぎないようにしましょう。
💡 補足:葉の色があまりに濃い緑色の場合は、逆に「肥料のあたえすぎ」の可能性もあります。
2.2 葉の形をチェック

オクラの葉は、栄養状態によって形や大きさがはっきり変化する野菜のひとつです。
順調に育っていれば、葉は大きく丸みを帯びた形になりますが、肥料が不足してくると切れ込みが深くなり、紅葉のような姿に変化します。
特に注意したいのは、花が咲いたあとや実がつきはじめたころ。
この時期はオクラがぐんと成長するタイミングで、多くの栄養を必要とします。
🌱 栽培初期に切れ込みの深い葉が多く見られるようなら、追肥のサインかもしれません。
葉の様子をよく観察して、実を育てる体力が足りているかをチェックしましょう。
2.3 葉の先端をチェック
トマトは、葉の先端部分に栄養バランスの変化が出やすい野菜です。
- 🌿 葉が内側に大きく巻いている場合:肥料過多の可能性があります。
- 🌿 葉が細長く、上を向いている場合:肥料不足の可能性があります。
- 🌿 少し下に巻くような形:正常なバランスが保たれている状態です。
とくにミニトマトは、もともと乾燥地帯原産のため、肥料が少なめでも育ちやすい性質があります。過剰に肥料を与えると、葉や茎ばかりが茂って実つきが悪くなることもあるため、注意しましょう。
✅ 葉の巻き具合は、追肥や水やりを見直すきっかけになる重要なサインです。
観察を習慣にして、トマトの声をキャッチしてみましょう!
3.実から読み解く追肥タイミング
野菜の実の様子をよく観察すると、追肥がうまくいっているかどうかが見えてきます。
「形」「数」「生長のスピード」などに注目してみましょう。
3.1 実が曲がっている
曲がったきゅうりができたことはありませんか?
これはもしかすると、肥料が不足しているサインかもしれません。
きゅうりが曲がる原因には、栄養不足、水不足、日照不足などがあり、株全体の元気が落ちてくると実の形にも影響が出てきます。
特に栄養不足の場合は、曲がった実が増える傾向があります。
🪴 特に注意したいタイミングは…
- 実が小さいまま大きくならない
- 実がつきはじめて、いくつか収穫した後(栽培中期)
- 全体の生長のスピードが落ちてきた時期
などです。

「最近、元気がないかも…?」と感じたら、追肥のタイミングかもしれません。
きゅうりが“へそを曲げている”ような形になったら、それは栄養が足りていない合図かもしれませんね💦
4. 期間で読み解く追肥のサイン
植物は、生長の段階によって必要とする栄養の量が変わってきます。とくに果菜類や短期で収穫を迎える野菜は、適切な時期に追肥を行うことで収量や品質が大きく変わってきます。
4.1 果菜類は定期的な追肥を心がける
果菜類(ナス、トマト、ピーマン、ゴーヤなど)は、花が咲いて実がなりはじめると、株の栄養をたくさん使います。元肥がなくなるタイミングはそれぞれ違うため初回の追肥は異なりますが、2回目以降は化成肥料などを使用する場合は2週間に1回程度のペースで定期的に追肥するのがおすすめです。
とくに収穫期に入ってからは、実を育てるエネルギーが必要になるため、追肥のタイミングが遅れると収量が落ちたり、実のつきが悪くなったりすることがあります。
📝 ワンポイント
定期的な追肥と同時に、葉色や花のつき方、実の状態をあわせて観察することが大切です。成長の様子に応じて、追肥の間隔や量を調整しましょう。

4.2 タイミングを見極めて追肥
【対象野菜:トウモロコシ、エダマメ、つるなしインゲン、サトイモなど】
これらの野菜は、定期的な追肥ではなく、栽培の節目ごとに「効かせたいタイミングで1〜2回追肥する」のがコツです。ポイントをおさえるだけで、実の太りや収穫量にしっかり違いが出てきます。

✅ トウモロコシ
草丈が20cmほどになった最後の間引き後と、雄穂(おすほ)が出る直前が追肥の目安です。追肥によって実に送るエネルギーが確保され、粒の並びや太り方に差が出ます。
✅ エダマメ・つるなしインゲン
追肥のベストタイミングは**「開花の少し前」と「莢が大きくなり始めた頃」**の2回。とくに花が咲いたあとは、急激に養分を必要とするため、1回目のタイミングがとても重要です。
✅ サトイモ
葉が展開しはじめる6月頃に1回目の追肥、さらに7月中旬~8月頃に2回目を行います。サトイモは後半にかけて芋が肥大するため、葉の勢いが落ちる前に栄養を蓄えさせることが大切です。
5. まとめ
追肥は、やみくもに与えるのではなく、野菜の「サイン」を見極めて、必要な時に必要な分だけ施すことが大切です。
本記事では、追肥のタイミングを見極めるために、
- 株全体のようす
- 葉の色・形・先端の変化
- 実のつき方や形の変化
- 栽培期間中の節目
といった視点から、具体的な野菜ごとに紹介してきました。
特に初心者の方は、「この時期にこれくらい」といった定期的な追肥に頼りがちですが、葉や実の変化を観察する力をつけていくことで、より元気な野菜を育てることができるようになります。
しま農研では、栽培の“調子”を見ながら追肥を加減することを意識しながら、日々の実験や観察を続けています。ぜひこの記事を参考に、あなたの家庭菜園でも追肥の「見極め力」を身につけてみてください。
👉 「追肥の基本と実践ガイド」では、しま農研の追肥ノウハウをさらに詳しくまとめています。
ぜひあわせてチェックしてみてください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!






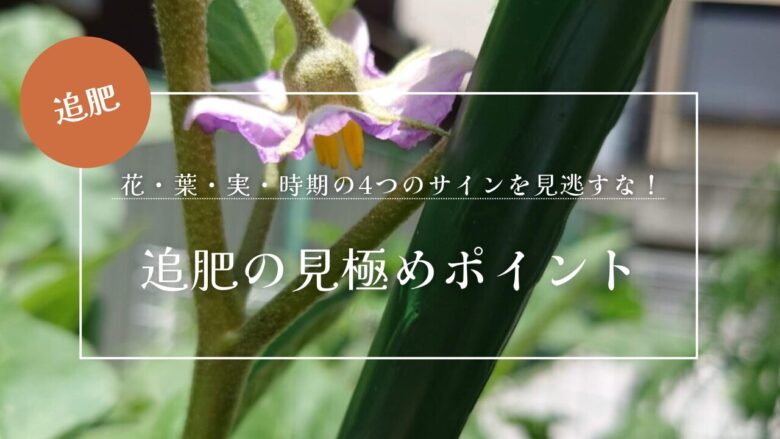



コメント